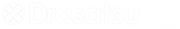最近、まるで犬のように4本の足で軽やかに動くロボットの映像を見かけたことはありませんか?

足場の悪い場所でもスイスイと進み、階段を登り、高い運動能力を備えて時にはバク転をするロボットもあります。
そんな四足歩行ロボットが今、世界中で注目を集めています。
「ロボット」と聞くと、人間の形をした二足歩行ロボットや、掃除ロボットのようにタイヤで動くものを思い浮かべる人が多いかもしれません。しかし、実は動物のようなロボットこそが、次の主役になる可能性が多いにあるのです。
ロボットとは
ロボットとは、センサーや人工知能などを活用し、外部環境を認識しながら自律的または遠隔操作で動作する機械のことです。
近年注目を集めるロボットは、これまで工場などで活躍していた単なる自動装置とは異なり、状況に応じて判断や行動の切り替えができる点が特徴です。産業、医療、災害対応など幅広い分野で活躍しています。
あらゆる分野への活用が期待される四足歩行ロボット
四足歩行ロボットとは、その名のとおり4本の脚で動くロボットのことです。見た目は犬や猫、あるいは馬やヤギに似ているものもあります。
脚が4本あることでバランスを取りやすく、ぬかるみやガタガタした道など、タイヤや二足歩行ロボットでは動きにくい場所でもスムーズに移動できます。
「動物の動きを真似てつくられている」と言えばイメージしやすいでしょう。

こうしたバイオミメティクス(生物模倣)の技術を使うことで、より自然で柔軟な動きが可能になります。
まるで本物の動物のように軽やかに歩き、段差や階段も難なく乗り越えるその姿に、多くの人が驚くと思います。
技術的な仕組み
四足歩行ロボットは「バランス」「制御」「感知」という3の大きな柱が基になっています。
四足歩行ロボットは、4本の足を交互に動かして歩きます。
この、「足の順番」や「タイミング」はあらかじめプログラムされているだけでなく、状況に応じてリアルタイムに変化することもあります。
(平坦な道ではスムーズに歩き、斜面や段差ではゆっくり動く等)
犬のように左右交互に動かしたり、斜めの脚を同時に動かしたりすることでバランスを保ちます。
2025年最新では、AI歩行制御アルゴリズムを搭載し、安定した歩行を実現しています。
またロボットは目の代わりにカメラ、LiDAR(レーザー測量)、IMU(加速度・ジャイロセンサー)などを使って周囲の状況を取得します。
地面の凹凸、障害物の位置、坂道の傾きなどをリアルタイムで感知し、姿勢を調整できるのです。
最近のロボットでは、AIが歩くルートを考えたり、障害物を避けたりといった判断も行います。
自律的に道を選んで歩く「ナビゲーションAI」や新しい地形でも素早く適応する「機械学習(ディープラーニング)で、ロボット自身が経験から学び、歩き方を改善していく技術も進化中です。
なぜ今、四足歩行ロボットが必要なのか?
これまでのロボットと言えば、多くの人が想像したのは鉄腕アトムやマグマ大使のような自らの判断で行動する自律型ロボットや、鉄人28号やジャイアントロボのようにリモコンで人間の指示通りに動く操縦型ロボットだと思いますが、考えてみればどれも二足歩行でしたね。
現実でも車輪で移動するタイプや二足歩行が主流でしたが、凹凸のある地面や障害物が多い環境ではうまく動けないという弱点がありました。そんな中注目されたのが四足歩行ロボットです。
人工知能やセンサー技術の進化によって、自立移動や状況判断も可能になりつつあります。今まさに、現実の課題に対応できるロボットとして、四足歩行型が注目されているのです。
四足歩行ロボットの活躍の場
本格的な社会実装はこれからになりますが、四足歩行ロボットが具体的にどのようなシーンでの活用が期待されているのかご紹介します。
災害現場・救助活動
足元の悪い瓦礫の中も移動可能なため、地震や崩落現場など、人間や車両型ロボットでは進入困難な場所でも、四足歩行ロボットなら安定して移動できます。
センサーやカメラを搭載しているので、状況確認だけでなく、生存者の確認といった人命救助の観点でも活用が可能です。
雪・砂漠・山岳地帯など、さまざまな地形に対応できるモデルが開発されています。
インフラ点検・建設現場
工場や発電所の点検、建設現場や警備など、特に人が立ち入りにくい危険な場所や不整地での点検・調査にも適した技術です。
空からはドローンが調査を行い、地上では四足歩行ロボットが巡回するといった「スマート点検」の導入を検討している企業も増えてきています。
充電や荒天時の対応、盗難対策といった課題はありますが、現地まで直接人が行かなくても、遠隔ですべてコントロールできる未来はそう遠くありません。
特に人手不足で悩む企業や、アクセスの悪い地域に広大な敷地を持つ発電所等にも向いているでしょう。
▼赤外線カメラ搭載モデルは、インフラ点検や災害対応など、幅広い用途で利活用が進んでいます
☆【点検業務用ドローン】DJI Matrice赤外線カメラ搭載ドローン比較
四足歩行ロボットのメリット・デメリット

工夫次第であらゆる場面での活用が期待できる技術ですが、デメリットもあります。
比較的手ごろな価格で購入可能なモデルも発売されていますが、実際に現場で稼働できるだけのスペックを備えているのか、結局運用コストが大きくなるといったことにならないか、事前に確認が必要です。
四足歩行ロボットを導入するメリット
- 遠隔操作が可能な為、現場に行くことなく点検・調査等の業務を遂行できる
- ケガのリスクがある足場の悪い場所でも、ロボットだけを派遣すれば安全に調査を実施できる
メリットとしては、まず上記が挙げられます。
一見ロボットには厳しそうに思える急勾配でも、適したパーツを持つモデルなら難なく上り下りが可能です。(対応できる地形はモデルにより大幅に異なります)
四足歩行ロボットを導入するデメリット
- 荒天時の対応、盗難対策が必要なため、完全無人運用には課題がある
- 地形や地面の状態によっては、機動性に影響を及ぼす可能性がある
実際に地上を歩き、充電中もドック等の中に入るわけではないため、完全に無人で稼働させるためには、雨天時・荒天時の対応や、盗難対策を考える必要もあります。
現場に応じた機能を追加する開発も可能ですが、導入費用は高額になります。
また急な角度や悪路も移動できるという特徴を持ちますが、例えば雨上がりですべる草地においては移動できなくなったり、砂利が崩れて滑り落ちてしまうというケースも発生することがあります。
どこへでもぐんぐん進んでいけるというよりは、ある程度ロボットが通る為に整備をしたり、定期的に除草したりといったフォローは必要です。
今後の展望

四足歩行ロボット市場の後押しとして、あらゆる作業の自動化・効率化の需要が近年急激に増加していること、人的コストが大きく人手不足が深刻な分野におけるIT技術の導入が積極的に行われていること(補助金対象の拡大等)、AIをはじめとする技術の進化が目覚ましいことが挙げられます。
ドローンのように、四足歩行ロボットが身近な存在となるまでは時間がかかることが予想されますが、開発者による実証実験が繰り返し行われ、点検や物流、警備等さまざまな現場で試験的に導入が開始されています。
今後は天候に左右されない堅牢な設計や、ロボット自体の盗難対策、長時間稼働への対応、悪路にも対応できる設計等、進化し続ける技術だと期待されています。
課題はまだあるものの、技術の進歩とともに四足歩行ロボットは着実に実用化へと近づいています。
近い将来、私たちの暮らしや働き方の中に、当たり前のように四足歩行ロボットが存在する――そんな未来がすぐそこまで来ているのかもしれません。
 ログイン
ログイン