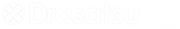国土交通省が施行した国家資格制度がなければ、重要なシーンでの飛行が制限されるリスクが高まっているのをご存じでしょうか?
国家資格について知らないことで、ビジネスチャンスを逃したり、法改正への対応が遅れたりする可能性も。
本記事では「無人航空機操縦士国家資格(通称:ドローンの国家資格)」の内容、費用、難易度、民間資格との違いをわかりやすく解説します。

国土交通省が発行する技能証明「ドローンの国家資格」とは?
国土交通省が発行しているドローンの国家資格とは2022年12月から創設した制度で、現在「二等無人航空機操縦士資格」と「一等無人航空機操縦士資格」の2種類の資格があります。
これらの資格は、国内におけるドローン操縦の安全性を高め、ドローン利用の拡大を促進することを目的としています。
ドローンの国家資格には受験資格が設けられています
1.16歳以上であること
2.航空法の規定により国土交通省から本試験の受験が停止されていないこと
2に関しては過去の犯罪歴やドローンの飛行で重大な過失があった場合対象となるものです。この条件に該当しなければ、受験を受けることができます。
では、この一等無人航空機操縦士資格と二等無人航空機操縦士資格の違いや、民間資格と何が違うのか紹介していきます。
ドローンの国家資格と民間資格の違いは?
まず、国家資格と民間資格の違いとしては発行主体の違いです。
ドローンの国家資格は国が発行し、管轄省庁は国土交通省となっています。
一方民間資格は、資格発行団体は民間の企業や社団法人となっています。
発行元の違いは、国家資格と民間資格の代表的な違いの一つです。
もう一つの違いとしては、ドローンの国家資格「無人航空機操縦士資格」は国の法律に基づいて資格が設けられていますが、民間資格は国家資格と異なり、取得した場合でも法的な効力を持っていません。
これまで民間資格を取得していることで飛行申請時に提出する書類が簡略化できるという恩恵がありましたが、これも2025年の12月5日で終了となります。
民間資格ではこういった効力がなくなるため、飛行申請で書類の簡略化が可能なのは、今後国家資格のみとなります。
飛行申請に関わる部分も国家資格と民間資格の違いになります。
また一等無人航空機操縦士の資格保有者のみになりますが、国家資格を保有しているとレベル4の飛行にあたる第三者上空で、補助員なしの目視外飛行の飛行申請ができるということも国家資格の民間資格の大きな違いと言えます。
ドローンの飛行において資格の取得は必須ではありませんが、国家資格を取得することにより、さまざまな場面でドローンを活用できるようになるのです。
ドローンの国家資格一等と二等の違いは?
次にドローンの国家資格「無人航空機操縦士資格」の一等と二等の違いについて紹介します。
無人航空機操縦士の一等と二等の違いはドローンで飛行可能な領域が違います。
一等無人航空機操縦士資格は、航空法におけるカテゴリー3に分類されるレベル4飛行、つまり有人地帯における補助者なしの目視外飛行を含む、立ち入り禁止措置を講じず特定飛行を行う場合、資格の保有に加えて、飛行ごとの許可・承認を取得することで、該当の飛行が可能となります。
一等無人航空機操縦士の資格を取得しただけでレベル4に当たる飛行ができるわけではありません。必ず申請を通す必要があるということを理解しておく必要があります。
二等無人航空機操縦士ではいわゆる「レベル3.5」にあたる飛行(立入管理措置を講じたうえでの目視外飛行など)が可能です。
ただし、一等無人航空機操縦士資格のように有人地帯における補助者なしの目視外飛行はできません。
有人地帯において補助者なしの目視外飛行ができるかできないかが一等と二等の無人航空機操縦士資格の違いです。
ドローンの国家資格を取るべき人は?
現在、日本でドローンを飛行させるにあたって、資格の保有が必須ではありません。
わざわざドローンの国家資格を取る必要があるのでしょうか?そのようにお考えの方もいらっしゃるはずです。
どのような方がドローンの国家資格を取得すべきなのでしょうか。
まずは、仕事でドローンを使うことが見込まれる方です。仕事でドローンを使う場合とは、ドローンをただ飛行させるだけでなく、測量や点検、またはイベントで大人数の近くで飛ばす場合など特殊かつ技術が必要な飛行をする場合です。
国家資格を保有していることで、特定の飛行も申請を通せるようになることや、取引先の信頼獲得にもつながります。
2つ目のパターンは既に民間資格を取得している方です。
先述したように2025年の12月5日で民間資格では飛行申請の簡略化が出来ないようになります。国家資格保有者のみ飛行可能なレベルもあるため、国家資格を保有することでメリットがあるのです。
飛行技術系に関する民間資格を既に保有されている方であれば、国家資格取得の際にも共通して生かせる知識や技術が備わっていると思います。
未経験の方に比べると合格しやすいことからも、国家資格の取得を目指すべきなのです。
国土交通省が発行する技能証明「ドローン国家資格」の取得方法
ドローンの国家資格「無人航空機操縦士資格」の資格取得に関する難易度や費用面について紹介いたします。
ドローンの国家資格を取得する難易度は?
国家資格取得は法律に基づいているものなので、民間資格よりも難易度は高いと言われています。
明確な合格率は出ていませんが、公表された合格率はありませんが、受験者の声などから50%〜60%程度と推定されています。
独学でもドローンスクールに通う場合でも基本的な飛行知識や飛行技術はもちろん、安全飛行に関わる航空法などの法律面での知識も求められます。
国土交通省が制度を施行している一等無⼈航空機操縦士実地試験実施細則では、実地試験は、100点の持ち点からの減点式採点法とし、各試験科目終了時に、80点以上の持ち点を確保した受験者を合格とする、と記載されています。
一等の机上試験は75分間に70問を解いて60問程度は正解しなければなりません。
一方二等無人航空機操縦士資格の細則では、実地試験は、100点の持ち点からの減点式採点法とし、各試験科目終了時に、70点以上の持ち点を確保した受験者を合格とする、と記載されています。
二等の机上試験であれば30分間に50問解いて35問以上の正答率を出す必要があります。
一等・二等ともに試験の手順としては、
1 机上試験
2 口述試験(飛行前点検)
3 実技試験 (飛行試験)
4 口述試験(飛行後の点検及び記録)
5 口述試験(事故、重大インシデントの報告及びその対応)
となっています。
実技試験などに関しては8の字旋回などをコースから逸脱せずに行うことや、緊急時の着陸手順を対地上センサーを切った状態で完全マニュアル操作で行う試験などがあります。
机上試験に合格しても、飛行技術を問う試験に中々合格できないという方もいらっしゃるということです。
加点方式ではなく、減点方式のため、1つ1つの動作確認や機材のチェックなどをしっかり頭にいれて臨む必要があります。
ドローンの国家資格取得にかかる費用は?
二等無人航空機操縦士資格の取得にかかる費用は受講するスクールによりますが、10万円前後~30万円程で、一等無人航空機操縦士の場合は50万円以上、初学者の場合は100万円以上の費用がかかるスクールもあります。
民間資格に比べると、取得までの費用はやはり高額となっています。
スクールで無人航空機操縦士資格の取得を目指す場合は、スクールによって費用が異なるので、受講を検討しているスクールに事前に確認しておきましょう。
独学の場合は、スクールに通わずに資格の取得を目指すため、発生する費用としては、受験料と勉強用の教科書代、試験用のドローンを保有していなければ、機材購入もしくはレンタル代、練習場所の費用となります。
国家資格の試験費用は学科試験が一等で9,900円、二等で8,800円、実地試験が一等で22,200円、二等の場合は20,400円となっています。
身体検査代は、オンライン申請で5,200円、対面受診では最大19,900円程度です。国家資格の取得後、新規交付料金として3,000円発生します。
また無人航空機操縦士資格には3年に一度資格の更新が必要となります(更新費用:2,850円)。
民間資格でも資格により更新費用がありますが、更新費用が1万円以上の民間資格もあるので、長期的に見ると民間資格よりお得です。
独学でも受験料が最低でも37,400円かかりますので、教科書代や練習場を借りる代金など含めると最低でも5万円以上はかかりますが、1発合格さえできればスクールに通うより断然安い費用で国家資格を取得できる可能性があります。
ただし、一人で受験に向かうため、国家資格に求められる知識や技術が身に付いているか確認が難しいことは認識しなければなりません。
まとめ
今回はドローンの国家資格について紹介してきました。
取得に向けては民間資格よりも難易度は高く感じるかもしれませんが、今後ドローンを使ったビジネスを行いたい方や、飛行申請が必要な特殊な飛行をさせる可能性が高い方は取得することをおすすめします!
ドロサツ‼では民間資格から国家資格の取得までを支援しております。資格取得にご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。
また、国家資格の実技試験練習用の機材レンタルも行っております。国家資格取得用に練習機材も併せて検討してみてください。
 ログイン
ログイン