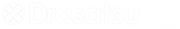「目視外飛行ってどんな飛行?」「自分の飛ばし方が違法だったらどうしよう…」そんな不安を持つドローン操縦者も少なくありません。

ドローンの目視外飛行は、知らないうちに規制の対象となり、違反リスクを抱える可能性があります。「どこまでが目視外飛行に該当するのか」といった明確な基準を把握していないと、知らずに法律に違反してしまうおそれがあります。
事故やトラブルが発生すれば、損害賠償などの責任を問われる恐れも。
本記事では、ドローンの目視外飛行の定義や法規制について詳しく解説し、安全に飛行させるための資格取得のポイントも紹介します。今後の厳格な取り締まりに備え、正しい知識を身につけましょう。
▼運用に必要な各種基礎知識、業務の一連の処理や手続き、実際の測量方法、データ解析まで習得するプログラムもあります
ドローンの目視外飛行とは?どのような飛行方法なのか理解しよう
ドローンの活用が広がる中でよく耳にする目視外飛行という言葉ですが、目視外飛行は、産業や物流の現場で欠かせない技術です。
ここでは、目視飛行とは何か、基本を分かりやすく解説します。
どんな場面でドローンは目視外飛行が必要になる?
そんな目視外飛行が、実際にどう活用されているのか、いくつかの場面と注意点を紹介します。

ケース①建物が多い場所でドローンを飛行させる
ドローンの目視外飛行とは、操縦者がドローンを直接見ないで飛行させることです。
建物が密集する都市部では、操縦者の目からドローンがすぐに見えなくなるため、目視外飛行となるケースが多くなります。しかし、こうした場所では目視外飛行が原則禁止されており、飛行には事前の許可が必要です。
DID(人口集中地区)上空では飛行が禁止されているので、そのための許可が必要です。
条件が厳しいのは、人口密集地であるため、安全確保の観点から当然といえるでしょう。万一事故でも起きたら大変な規模の惨事になりかねません。
ケース②ドローンを広い範囲で飛行させる
農地や山林、災害現場など、広大なエリアを対象とする作業では、ドローンを長距離にわたって飛行させる必要があります。こうした状況では、操縦者からドローンが離れてしまうため目視外飛行が前提になります。
たとえば、農薬散布や作物の生育状況を調べる農業分野、山間部のインフラ点検、広域での人命救助などの活用例があります。
ドローンが自律的に飛行し、リアルタイムでデータを送信することで、効率的に作業を進めることができます。
広範囲で目視外飛行を安全に行うためには、GPSや高度な飛行管理システムの導入が必要です。
また、広範囲を飛行させる際には、第三者との距離が30m未満にならないか、DID(人口集中地区)外であるか、高度150m以上ではないか、空港周辺に該当しないか等、各種の法的条件を確認する必要があります。
万が一事故が起きた場合はただちに報告する事。また飲酒状態での飛行は禁止されています。
ケース③高度を上げてドローンを飛行させる
高度をあげての飛行は目視外飛行が必要になる典型的な場面です。
航空法では、地表または水面から150m以上の高さを飛行する場合、原則として国土交通大臣の許可が必要です。航空機の運航に支障をきたす可能性があるためです。
点検や測量、空撮などは上空から広範囲を捉える必要があり、ある程度の高度が必要です。たとえば、送電線や風力発電設備など高所インフラの点検、災害時の被害状況の確認では高度100メートル以上が必要になることもあります。
そもそもドローンにはそれぞれにスペックの面で飛行可能な高さの限度があります。それを超える高度で飛ばないよう注意が必要です。高高度の飛行には国土交通大臣の許可が必要ですが、飛行エリア、飛行高度、飛行目的等を具体的に示す必要があります。あらかじめ航空法の制限や飛行計画の確認と調整、飛行可能な高度の確認などを怠りなくチェックしておくのが良いでしょう。
ドローンの目視外飛行をするために必要な申請や免許とは?
目視外飛行は誰でも自由にできるわけではなく、法律に基づいた手続きは許可が必要になります。
ここからは、ドローンを使っての目視外飛行の際の必要とされる申請や免許について説明します。

ドローンの目視外飛行申請に必要な5つの条件とは?
ドローンで目視外飛行を行うには、国土交通省の許可が必要です。申請には次のような条件があります。
- 基本的な操縦技術を習得しているか
- 自動操縦システムを装備しているか
- 地上から機体の位置や異常を把握できるか
- 電波途絶等の不具合時に危機回避機能が正常に作動するか
- 10時間以上の飛行実績を有しているか
これ以外でも、補助者無しで目視外飛行を行う場合は、補助者の役割を代替できる機体や地上設備を配備する必要があります。さらに、安全管理体制や飛行計画を立てる事も必要です。多くの条件や設備が求められるため、十分な準備が必要です。
ドローン目視外飛行の許可を取るための具体的な手順【DIPS2.0】
ドローンを飛行させるうえで、避けて通れない関門の一つが「目視外飛行」です。
ドローンの原則は、操縦者が機体を目視しながらの操作することですが、実際の運用では様々な理由でカメラの映像を頼りに操縦する時もあるでしょう。
そのような目視外飛行を行うためには、事前に国土交通省への申請が必要です。
①DIPS2.0にアクセス&アカウント作成
まず、国土交通省の「ドローン基盤情報システム(DIPS2.0)」からインターネット上で申請手続きを行います。
ドローン基盤情報システムのトップページにアクセスし、「無人航空機飛行許可申請」という項目に、初めて申請される場合は、「はじめての方」を選択してアカウントを開設してください
ドローン情報基盤システム2.0
②機体情報を登録
飛行させるドローンの機体情報(製造社・型番、機体番号など)などを入力します。
③操縦者情報を登録
操縦者の氏名、生年月日、住所のほか、技能証明書や飛行経験も登録し、国家資格を取得している場合は入力します。
※国家資格を取得していると、申請が簡略化されることがあります。
④飛行計画の登録
どこで、いつ、どのような目的で目視外飛行を行うかを記載、飛行ルートや高度、飛行方法を明記します。
⑤許可・承認の申請
上記の情報をもとに、「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書」をDIPS2.0 内で作成します。
目視外飛行申請にかかる日数
審査に一定期間を要する為、飛行開始の少なくとも10開庁日前(土日祝日を除く)までに申請書を提出してください。補正さえ出なければ申請から10開庁日で飛行許可が出ます。
目視外飛行申請に掛かる費用
自身で行う飛行申請に関しては無料ですが、例えば行政書士へ代行を依頼する場合は費用が発生します。
価格は飛行計画や場所、難易度(調整が必要となる関係者が多数存在する等)によって大幅に異なる為、事前に打ち合わせが必要です。
「独自マニュアル」の作成が必要となる申請については、一般的に申請費用が高額になる傾向にあります。
ドローンの目視外飛行で法律違反とされるケース
ドローンの利便性が注目される一方で、操縦には厳格なルールがあります。
操縦に慣れればこんなに楽しいことはありませんが、世の中にはちゃんと守らなければならぬことも一杯有ります。ルールを軽視すれば思わぬ違反となり罰則を受ける可能性もあります。
実際に法律違反とされた事例を紹介します。

ケース①SNS投稿がきっかけで発覚する違反
ドローンの目視外飛行に関する法律違反の事例として、SNSやYouTubeにアップロードした動画がきっかけで書類送検に至ったケースがあります。
航空法に違反して撮影された動画が以前は多かったため、今でも動画がアップされると違反でなくても違反では?とコメントが付くことが多いようです。映像の公開では細心の注意が必要です。
ケース②花火大会の空に違反飛行
2023年8月、静岡県沼津市で開催され花火大会で、ドローンの空撮が実施されましたが「飛行計画の通報」がされていない不備が判明しました。飛行計画の通報を怠ると違反となります。
一般人の通報で発覚したとされています。詳細は明らかにされていませんが、恐らく一般の方がDIPSの飛行計画を確認して通報されていないことに気づかれた!ということが考えられます。
ちなみに「DIPS」とは、国土交通省が運用する、ドローン情報基盤システムの事です。
ケース③無許可で目視外飛行→書類送検
2021年には北海道で男性が農業用ドローンを使用して、補助者を置かずに目視外飛行で自動飛行を実施しました。
国土交通省の許可・承認を受けておらず。航空法違反で書類送検されています。本人は「違反とは知らなかった」と述べていますが、法律違反は知らなかったでは済まされないことに注意が必要です。
ドローンの国家資格を取得すればいつでも目視外飛行が可能になる?
一等または二等無人航空機操縦士の国家資格を取得すれば、目視外飛行の承認申請が簡略化される場合があります。ただし、どこでも自由に飛ばせるようになるわけではなく、飛行には個別の申請と許可が必要です。
一等/二等無人航空機操縦士という国家資格は「操縦者の信頼が証明された」ことであって、目視外飛行には手順をふんだ申請が必要です。
☆国土交通省が発行する技能証明「ドローンの国家資格」を取るとできることは?
☆2025年最新!ドローンの国家資格2等ライセンスを徹底解説!
まとめ
ドローンの目視外飛行とは、操縦者が機体を直接視認せずに行う飛行方法です。
この飛行には航空法に基づいた申請手続きが必要で、無条件に実施できるわけではありません。国土交通省への許可申請をはじめ、操縦資格や技術の証明、具体的な飛行計画の提出が求められます。
特に業務利用を前提とする場合は、制度の理解を深め、万全の準備と安全管理体制を整えることが不可欠です。正しい知識をもって、安全かつ適正に目視外飛行を行いましょう。
 ログイン
ログイン