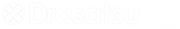最近、ドローンは趣味の用途に限らず、測量や点検等、ビジネスを目的として幅広く活用されるようになってきています。
それに伴い、ドローンの操縦技術証明として民間資格に注目が集まっていますが、国家資格との違いや、民間資格を取得することのメリットなどわからないことも多いのではないでしょうか。
そこで、今回はドローンの民間資格の取得するメリットや取得方法、飛行申請との関係まで、初心者が持つことの多い疑問を徹底解説します!

ドローンの民間資格とは?国家資格との違い
ドローンの資格は、主に民間資格と国家資格の2種類に分かれます、
「ドローン 資格」と検索すると、2つが混在して紹介されていたりしますが、この違いは何なのでしょうか?
コンシューマー向けドローンが発売され始めてから早くも10年ほど経ちますが、これまでドローンに国家資格というものは無く、DJI・DPA・JUIDAなどの各ドローン団体が定める民間資格のみ存在していました。
(製品を正しく取り扱うために、各メーカーが定める独自のオペレーター資格等を除く)
国家資格は2022年12月に施行されたばかりの比較的新しい制度で、「一等無人航空機操縦士」と「二等無人航空機操縦士」の2つの国家資格があります。
ドローンの飛行はレベル1~4に分類されますが、一等を取得すると最も難易度の高いレベル4飛行が認められ、二等の場合はレベル1~3の申請が不要になるといったメリットがあります。
※ただし、いずれの場合も認証済みの機体を使用することが前提となるのでご注意ください
現状、民間資格であってもレベル1~3の飛行が可能ですが、飛行する際はその度に国土交通省へ申請して許可を得る必要があります。
また、国家資格の一等無人航空機操縦士の資格を保有している場合、レベル3の飛行よりさらに高度な目視外・有人地帯・補助者なしでのドローンの飛行が可能なレベル4の飛行も可能となります。
民間資格ではこのレベル4に当たる飛行を認定する資格はありませんので、このことから、将来を見据えて・業務を拡大するために一等および二等の国家資格を取得する方が増えています。
しかし、認証された機体を使用しなければならないという部分でメリットを享受できないケースも多いため、今国家資格を取得すべきなのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

ドローンの民間資格を取得するメリット
国家資格に比べて、取得までの費用が安価で済むことが多いのも一つのメリットです。
また難易度も国家資格に比べると低く設定されているものがほとんどなので、ドローンの基本的知識や操縦技術を身に着けられるのもメリットと言えるでしょう。
いきなり国家資格を取得しようとすると、時間も費用もかかり、挫折・・・なんてことも起こらないとも限りません。
民間資格から基礎を固めていくというのも一つの方法としてお勧めです。
国家資格を取得する場合、ドローンスクールを活用する方法が合格への近道となりますが、その際にドローンの操縦経験によって費用が変わることがほとんどです。
初心者よりも経験者の方が受講費用を抑えられる傾向にあり、民間資格を取得していると経験者講習を受講できるので、結果的に初心者から国家資格を目指すよりも、民間資格を挟んだ方がトータルコストを抑えられるというのも大きなポイントです。
また、2025年の12月4日までではありますが、航空局のホームページに記載のあるホームページ掲載講習団体が発行する民間資格は、飛行申請時に技能証明として、一部書類提出の簡略化のメリットを受けることができます。
農業用ドローンを飛行させて農薬散布をする場合は、現状ドローンメーカー(DJIなど)や一般社団法人農林水産航空協会が発行している民間資格の取得がほぼ必須とされています。
こういったドローンの活用を考えている方は、まず国家資格よりも民間資格やメーカーが指定しているライセンスを優先して取得されることをお勧めします。
▼初心者でもわかるドローンの民間資格2025年の最新事情
☆結局どの資格を取ればいい?2025年最新ドローン民間資格一覧
ドローンの国家資格を取得するメリット
つづいて、ドローンの国家資格を取得するメリットをお伝えします。
まず、ドローンの国家資格は国の法律に基づいた資格になるため、難易度は民間資格より高い分、取得後の技能証明としては民間資格よりも有効な資格になります。
一例としては、二等無人航空機操縦士資格の取得で目視内の手動飛行にあたるレベル1から、無人地帯での目視外飛行(補助者なし)の飛行許可承認申請が免除されます。
※前述の通り認証された機体が必要です
また国家資格を取得すると、空撮に限らず測量や点検など幅広い分野でドローンを使った案件をもらえるケースも多いため、ビジネスとしての技能証明となるメリットの大きい資格と言えます。
ただし、国家資格の無人航空機操縦士の有効期間は一等・二等共に3年間となっているため、自動車の運転免許証と同じように更新する必要があります。
一度取れば安心ではなく、常にスキルを磨き続けて知識のアップデートを求められるということですね。
無人航空機操縦士の資格更新は、登録講習機関が実施する最新の知識・能力に関する無人航空機更新講習を修了する必要があります。
▼資格取得を検討しているという方は、ぜひ参考にしていただければと思います。
☆国家資格の無人航空機操縦士って何?詳細と取得方法や難易度を紹介
☆2025年最新!ドローンの国家資格2等ライセンスを徹底解説!
☆国土交通省が発行する技能証明「ドローンの国家資格」を取るとできることは?
★お勧めの取得方法
(国家資格取得のコストを抑えたい・確実に知識を身に着けたい方におすすめです)
①まずは民間資格を取得する
②国家資格の経験者講習を受講する
ドローンの民間資格を取得する方法

ここからはドローンの民間資格を取得する方法・順序を紹介していきます。
一概にどの資格も下記手順で受講するわけではありませんが、民間資格の受講手順として代表的なものを紹介します。
①民間資格の講習をスクールで受講する
スクールによって異なりますが、学科試験から実地試験のカリキュラムがあらかじめ組まれているものが多く、経験者向けのものでは1日数時間の座学講習とテストで取得できる資格もあります。
価格も日数もスクールによって異なるので、申し込む前に気になる資格をいくつか比較してみてはいかがでしょうか。
ドローンの操縦技術だけでなく、電波法や航空法などを学ぶことができる資格など様々な種類がありますので、ご自身が関心のあるものや身に着けたい知識に合致するものを選んで受講されることをお勧めします。
ドロサツ!!では、世界シェアNo.1のドローンメーカーDJIが指定する「DJI CAMPスペシャリスト認定講習」の実施を行っています。
その後、国家資格の取得を目指される方には、提携スクールによる国家資格講習のご案内も可能です。
②カリキュラム修了後に民間資格認定試験を受ける
一通りカリキュラムを修了した後、最後に資格認定試験を受験します。
試験は知識を問われる学科試験と、飛行技術を測定する実地試験の2つになることが大半です。
飛行技術を認定する試験は学科試験と会場が異なる場合もあります。基本的に国家資格の試験を行っている登録講習機関であれば対応しているケースが多いです。
合格後認定証をもらい、晴れて資格取得となります。
ドローン民間資格による飛行許可申請の最新事情
これまで、航空局のホームページに記載がある、JUIDAやDPAなどの「ホームページ掲載講習団体」が発行する民間資格はDIPS2.0上で飛行許可申請を行う際に必要な「操縦者の技能証明(飛行実績の証明)」として利用でき、一部書類の簡略化をすることができました。
しかし、ドローンの民間資格による飛行許可申請簡略化の措置は2025年12月5日以降、国家資格のみ適用することを国土交通省が発表しているため、2025年12月4日までで民間資格による飛行申請の簡略化措置はなくなります。
そのため、今後ドローンの資格取得を目指す方や、高度な飛行技術を用いてビジネスを行いたい方は、最終的に国家資格を目指すことになるかと思います。
その為の準備として、または費用を抑えるために、今民間資格を取得することはお勧めです。
もちろん国家資格の取得は考えておらず、これまでに民間資格を取得されたという方も、その資格は飛行技術や知識の証明として使うことができるため、無駄にはなりません。
しかし、飛行申請を出してドローンを飛行させることが多い場合は、今後国家資格の取得も視野に入れるべきかもしれません。
まとめ

ドローンの民間資格の取得はドローンの技術・知識習得の第一歩として、初心者の方に特におすすめできる資格です。
但し、一口に資格と言っても、千差万別で取得したからと言ってどの現場でも万能に使えるわけではありません。
ドローンの飛行に関する知識を身に着けたいのか、安全管理や特定の機材の技術習得など様々です。
金額も決して安いものばかりではないので、ご自身がドローンの資格を取得してその後どのようにしたいかビジョンを作ってから取得することをお勧めします。
また、飛行申請を都度提出するような高度な飛行をドローンで行う機会が多い場合は、国家資格の取得をお勧めします。
ドロサツ‼では提携ドローンスクールとともに、民間資格から国家資格の取得支援も行っております。
ドローンでの資格取得に関心のある方は、是非お気軽にお問い合わせください。
 ログイン
ログイン