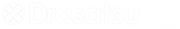ドローンの活用は、民間企業から国・自治体まであらゆる領域へと拡大しています。
農業・建設・防災といった産業分野はもちろん、観光PRやインフラ点検、災害対応など、多彩な事例が生まれています。
この記事では、最新のドローン活用事例を紹介するとともに、今後さらに期待される分野についても展望します。ドローン導入を検討中の方はぜひ参考にしてください。

ドローンはどのような分野や事例で広く活用されているのか
ドローンが使用されている業界の全体を俯瞰すると、ドローンの活用分野は「民間による業務効率化」と「自治体・公共分野による社会インフラ対策」に大きく二極化しています。
特に精密な農業支援、建設・インフラ点検、防災・災害対策は、技術の進化と相まって社会実装が急速に進んでいます。以下の事例でも紹介いたしますが、ドローンはどの分野でも「効率化」「精度向上」「安全確保」といった課題解決を担い、今後ますます幅広く様々な分野で活用されることが予想されます。
農業・物流・点検で進む民間ドローンの実用化
民間分野におけるドローンの導入は、従来の業務を効率化・省力化する技術として急速に広がっています。特に農業、物流、インフラ点検の現場では、課題解決に直結する手段として注目されています。
農業分野では、農薬や肥料の自動散布、圃場のセンシングによる作物の生育状態の可視化が進んでいます。ドローンにAIを搭載し、空撮画像から植物の健康状態や病害の兆候を把握する技術も普及しています。
人手不足や作業の省力化といった課題への対応として、スマート農業の中心的存在になりつつあります。
物流では、過疎地や災害時の代替手段としてドローン配送の活用が進行中です。特に山間部や離島など、トラックや人が入りにくい地域でのラストワンマイルといわれる遠隔地配送の実績が出てきています。
例として、豪雪や豪雨などで一時的に交通網が遮断された際、収穫物や医薬品などの緊急物資を空輸する事例が増えており、災害に強い新たな物流インフラとしての役割が期待されています。
さらに、建物やインフラ設備の点検にもドローンは有効です。

高所や狭所など人が立ち入るのが困難な場所の点検を、ドローンが代替することで作業の安全性と効率が大幅に向上しています。
橋梁、送電線、ビルの外壁など、従来は時間とコストがかかっていた検査が短時間で済むようになり、民間建設会社や点検業者の間でも導入が加速しています。
このように、ドローンは農業の高度化、物流の柔軟化、インフラ管理の効率化といった多様な場面で「当たり前のツール」になりつつあり、今後さらに多様な業務への応用が期待されています。
民間でのドローンの活用事例を紹介
民間企業においても、ドローンの実用化が急速に進んでおり、業種を問わずさまざまな分野で活用が広がっています。注目されているのが、農業、物流、そしてインフラ点検といった分野です。
農業分野では、ドローンを活用した農薬や肥料の散布、自動飛行による生育状況のモニタリングなどが行われており、人手不足の解消や作業効率の向上に大きく貢献しています。AIやセンサー技術と連携することで、作物の状態を解析しながら必要な場所にだけ資材を散布する「精密農業」も進化を続けています。
物流分野では、遠隔地や災害時の物資輸送を目的としたドローン配送の実証実験が活発に行われています。特に山間部や離島など、従来の輸送手段が不便な地域に対して、ドローンを用いた迅速な配送が注目を集めています。

また、都市部においても無人配送の実現に向けた取り組みが進められており、今後の商用化に期待が寄せられています。
▼ドローンを活用することで一連の作業コストも大幅に減少
☆商業現場で活躍するDJI製ドローン:効率化と安全性の向上について
インフラ点検においても、ドローンはその高い利便性を発揮しています。
橋梁やダム、送電線などの高所や危険箇所における点検を、人が立ち入ることなく安全かつ迅速に行える点が最大の魅力です。赤外線カメラや高解像度カメラを搭載した機体を用いることで、劣化や亀裂などの微細な異常も見逃さずに捉えることが可能です。
これにより、保守管理の精度が向上し、長期的なコスト削減にもつながっています。
このように、民間企業におけるドローンの導入は業務の自動化・効率化を促進するだけでなく、安全性や精度の面でも大きな成果をあげています。
今後もさらに多様な分野での活用が広がることが期待されており、ドローンは企業活動を支える重要なツールとしてその存在感を増しています。
農業の自動化を進めるドローン活用事例
農業の現場では、少子高齢化や人手不足といった課題を背景に、自動化や省力化が求められています。そうした中、ドローンの導入が加速しており、さまざまな工程で効率化が実現しつつあります。
代表的な活用のひとつが、農薬や肥料の自動散布です。

従来の散布作業では時間や人手がかかっていたものの、ドローンを使えば広い農地にも短時間で均一に散布が可能になります。また、搭載されたセンサーが土壌や作物の状態を解析し、必要な部分にだけ薬剤を届ける「精密農業」にも対応しており、無駄を省いた資材の運用が可能です。
さらに、ドローンは空撮によって作物の生育状況を可視化することにも役立っています。
上空から取得した画像データをもとにNDVI(植生指数)などを解析すれば、作物の健康状態や異常の兆候を早期に把握することができます。これにより、病害虫の発生や水不足などへの迅速な対応が可能となり、収穫量や品質の安定にも貢献します。
最近では、種まきや苗の移植といった工程でもドローンの活用が始まっており、人の手で行っていた作業のさらなる自動化が期待されています。
加えて、取得した映像やデータはクラウドに蓄積され、AIによる解析結果をもとに営農計画を立てることも可能となっています。これにより、経験や勘に頼っていた判断がデータドリブンに変わりつつあり、農業経営の高度化も進んでいます。
このように、農業分野におけるドローンの活用は単なる省力化にとどまらず、精度の高い農作業と持続可能な農業経営を実現する基盤として大きな期待を集めています。
今後、さらに多くの農家や法人が導入を進めていくことが予想され、ドローンはスマート農業の中核技術として定着していくでしょう。
建設業界でのドローン測量・進捗管理の最前線
建設業界でも、ドローンの導入が急速に進み、測量や進捗管理の分野で革新的な変化をもたらしています。
従来、人手と時間をかけて行っていた地形測量や構造物の確認作業が、ドローンによって短時間かつ高精度に実施できるようになり、作業効率の大幅な向上が実現しています。

特に測量分野では、ドローンに搭載された高精細カメラやレーザースキャナー(LiDAR)を用いることで、広範囲の地形データを迅速に取得できます。これにより、三次元モデルの作成や土量計算が短時間で可能となり、設計から施工までのスピードが大きく改善されました。
これまで数日から一週間以上かかっていた現地測量が、わずか数時間で完了するケースも珍しくありません。
また、施工段階においては、ドローンが空撮した画像を用いて工事の進捗状況を可視化することができます。
上空からの定期的な撮影によって、資材の配置状況や工事の進行具合を記録・共有し、現場担当者や管理者、施主との情報共有をスムーズにします。
特に複数の工区が並行して進行する大規模プロジェクトでは、全体の管理精度を高める上でドローンが大きな力を発揮します。
さらに、進捗の記録と連動したBIM(Building Information Modeling)やCIM(Construction Information Modeling)との統合も進められており、設計情報と現場の実際のデータとの差異を可視化しながら管理できる体制が整いつつあります。
これは施工ミスの早期発見や再作業の防止にもつながり、品質向上とコスト削減の両立を実現するうえで欠かせない技術となっています。
こうした最新のドローン技術の活用により、建設現場はこれまで以上に「安全・効率・高品質」な現場運営が可能となっており、今後ますますその活用が進むと見込まれています。
特に少子高齢化による人手不足や現場の省人化が求められる中で、ドローンは建設業界の持続的成長を支える重要なツールとして位置づけられています。
国・自治体でのドローンの活用事例を紹介
国や自治体におけるドローンの活用は年々拡大しており、特に災害対応、防災訓練、インフラ点検、農業支援など、公共性の高い業務においてその有用性が認識されています。
国土交通省や消防庁、地方自治体などでは、現場の安全性を確保しつつ迅速な情報収集を可能にする手段としてドローンを導入。高所や人が立ち入れない危険区域での作業を代替し、人命を守るためのツールとしても重要な位置づけがなされています。
たとえば、災害時にはドローンによって土砂崩れや河川の氾濫箇所をいち早く特定し、救援ルートの選定や避難指示の判断材料として活用されます。
また、自治体主導の防災訓練でも、ドローンによる被害想定の可視化や、上空からのリアルタイム映像配信による現場の把握などにより、従来よりも効率的かつ現実的なシナリオが実現しています。
さらに、老朽化が進む公共インフラ(橋梁・トンネル・堤防など)の定期点検においても、ドローンは高精度カメラや赤外線センサーを活用して損傷や劣化の兆候を検出する役割を担っています。
人手不足や作業員の安全確保が求められる現場では、ドローンの導入により大幅な業務効率化とリスク低減が実現されています。
国や自治体におけるこうした取り組みは、今後の地域課題解決やスマートシティ化を進める上でも重要な施策の一環といえ、民間との連携による実証実験や運用体制の整備も急速に進んでいます。
ドローンは単なる飛行機器ではなく、行政の現場を支える実務的ツールとして、ますます欠かせない存在になりつつあるのです。
災害現場での迅速な状況把握と情報収集の事例
災害発生時、いち早く現場の状況を把握し、的確な初動対応を行うことは被害の拡大防止や人命救助に直結します。

その中で、ドローンは上空からの視点で広範囲の情報を短時間で収集できる利点を持ち、災害対応の現場で非常に重要な役割を担っています。
たとえば、2021年の静岡県熱海市で発生した大規模土石流災害では、発災直後から自治体および防災機関がドローンを活用し、被災範囲の確認や二次災害の危険性の有無を調査しました。
特に人が立ち入れない崩落現場に対し、ドローンによる高解像度の空撮画像と動画がリアルタイムで災害対策本部に送信され、避難指示や救助ルートの決定に貢献しました。
また、2020年の熊本県南部を襲った豪雨災害では、球磨川流域における氾濫状況の把握のため、国土交通省と熊本県が連携してドローンによる航空撮影を実施。
氾濫した水がどの範囲に及んでいるのか、橋梁や道路の損傷状況、孤立地域の有無などを即時に可視化し、ヘリコプターでは難しい狭隘地域の状況確認にも大きく寄与しました。
さらに、福島県では、ドローンと3Dマッピング技術を組み合わせて、震災後の津波被災地域の地形変化を測定し、復旧計画の基礎資料として活用した事例もあります。
このように、ドローンは災害時の情報収集だけでなく、復旧・復興計画の策定にも役立つ高度なツールとして注目されています。
従来、人的・時間的コストのかかっていた災害現場の調査が、ドローンの導入によって飛躍的に効率化されており、これまでのように災害発生から情報が集まるまでに数日かかっていたものが、わずか数時間、あるいはリアルタイムでの判断を可能にしています。今後も、災害時におけるドローンの配備と操作ノウハウの共有は、全国の自治体にとってますます重要な課題となっていくでしょう。
観光振興や景観管理での空撮ドローン活用
ドローンによる空撮は、観光地の魅力を引き出す新たな手段として注目されています。
これまで地上からは捉えきれなかった景観や風景を上空からダイナミックに撮影することで、観光資源の魅力を最大限に発信できるようになりました。さらに、景観の維持管理にもドローンの活用が広がっています。
例えば、長崎県の五島列島では、観光プロモーションの一環としてドローン空撮を活用し、美しい海岸線や世界遺産である教会群を上空から撮影。その映像を使ったPR動画は、国内外から高い評価を受け、来訪者数の増加につながっています。
また、北海道富良野市では、四季折々の花畑をドローンで空撮し、SNSや公式サイトでの情報発信を強化。特に海外からのインバウンド需要に効果を発揮しています。
景観管理の面では、歴史的建造物や山岳地帯など、人が立ち入りにくいエリアのモニタリングにもドローンが活躍しています。
京都市では、文化財保護の一環として寺院の屋根や構造物の点検をドローンで実施。破損箇所の早期発見や補修計画に役立てられています。
また、国立公園など広大な自然エリアでも、ドローンを使って森林の変化や植生の管理を行う事例が増加しています。
こうした取り組みにより、地域の魅力を映像で伝えるだけでなく、観光資源を守り、持続可能な観光地づくりに貢献する手段として、ドローンの役割はますます大きくなっています。
今後は、ARやVR技術と組み合わせたバーチャル観光の分野でも、ドローン空撮データが活用される可能性が広がっていくでしょう。
事例からみる今後ドローンの活用が広がると見込まれる分野
ここまでの事例を見てきて明らかになったのは、ドローンの活用は特定の業種に限らず、さまざまな分野において応用可能性を秘めているという点です。
では今後ドローンの活用が広がりそうな分野はどの分野なのでしょうか?ここでは簡単におさらいしていきます。
教育・研究分野での実習・観測ツールとしての展開
ドローンの活用は、教育・研究現場にも着実に広がりを見せています。従来の座学中心の学習スタイルに加え、実践的な技術や観察・分析力を養う手段としてドローンは注目されています。
高校や専門学校、大学では、ドローンを使った測量演習や環境観測の実習が取り入れられ、ICT教育やSTEM教育の一環として導入が進んでいます。
例えば、地理や地学の授業では地形の変化を上空から捉える空撮観測や、災害後の土砂崩れや浸水範囲の確認を模した演習を行うことで、学びのリアリティが増し、知識の定着にもつながります。
また、研究機関では、動植物の生態調査や、農業研究における作物の生育分析、気象データの収集などにドローンが活用されています。人が入りづらいエリアでも安全かつ効率的に情報を取得できるため、従来のフィールドワークに代わる手段として重宝されているのです。
今後は、プログラミングやAIとの連携によって、より高度なドローン制御を学ぶ実習や、観測データの分析・活用までを見据えた教育カリキュラムも求められるでしょう。
ドローンは単なる飛行機材にとどまらず、教育や研究の在り方そのものを進化させる新しいツールとなりつつあります。
海洋監視や密漁対策など海上安全分野での応用
海上安全の分野でも、ドローンの導入が着実に進んでいます。
これまで海上の監視や密漁対策といった業務は、船舶や人員による目視・巡回が中心でしたが、広大な海域の常時監視には限界がありました。そこで注目されているのが、ドローンを活用した空からのリアルタイム監視です。
実際、瀬戸内海や三重県沿岸部など一部の地域では、海上保安庁や自治体が試験的にドローンを活用して密漁防止のパトロールを行っています。
高性能カメラや赤外線センサーを搭載したドローンが、夜間や早朝でも不審な船舶の接近を検知し、即座に管理者へ映像を転送する仕組みを構築。これにより、密漁者への迅速な対応や証拠映像の取得が可能となり、抑止効果も期待されています。
島しょ部や沖合における定期的な海洋資源の監視や、海洋ゴミの分布調査、さらには油の流出など環境事故発生時の初動確認にもドローンは有効です。
人の立ち入りが困難な場所でもドローンで状況を把握できるため、安全性と効率の両面で大きなメリットがあります。
今後は、AIによる自動識別機能や、長時間・長距離飛行可能な固定翼型ドローンの活用が進めば、より広範囲かつ継続的な海上監視体制の構築が可能になります。
漁業資源の保護や海洋環境の維持、安全な航行支援に至るまで、海の守り手としてドローンは重要な役割を担っていくことでしょう。
まとめ
ドローンは官民問わず、様々な分野で活用が広がってきています。
これまでは建設や空撮など特定の分野でドローンが活用されてきていましたが、今後は教育や海上監視といった分野での活用も見込まれるなど、その可能性は無限大と言えるでしょう。
ドローンの利活用は今や社会の常識となりつつあり、将来生活や産業のあらゆる場面で、ドローンが不可欠な存在になるかもしれません。
少しでもドローンに興味を持たれた方は、最新情報や機材などをチェックしてみて、気になる機材や活用方法があれば、お気軽にドロサツ‼にご相談ください。
 ログイン
ログイン