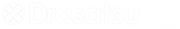農業現場でのドローン活用が急拡大していますが、導入しないことで作業効率や収穫量で大きく差がつく可能性があります。農薬散布や播種、圃場(ほじょう)管理など、農業用ドローンは多様な用途で活躍し、作業の負担軽減やコスト削減にも効果的。
本記事では、農業用ドローンの種類や具体的な活用事例を紹介し、導入のメリットと今後の農業における重要性について解説します。変化する農業の現場に取り残されないために、今こそ知識を深めましょう!

農業用ドローンの主な種類と特徴
農業に活用されるドローンとは、一般的なドローンとどのような違いや特徴があるのでしょうか。
農業用ドローンとは、田畑の上空を飛行し農薬や肥料を散布するだけでなく、果物の授粉作業にも利用可能です。
一般的にどのような種類があるのか、紹介していきます。
農薬肥料散布用ドローン
農業用ドローンと聞いてこの農薬散布や肥料散布を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
この農薬肥料散布用ドローンはその名の通り、農地や果樹園の上空を飛行し、満遍なく農薬や肥料を散布して農作物の生育や農産物を守ることを図っています。
これまで人が1日かけてやっていた農薬散布や肥料散布の作業効率化を実現しています。
最も一般的な農業用ドローンですが、導入には各メーカーや社団法人が発行する資格の取得が必須となることが多いです。
農作物等運搬用ドローン
最近では、物品運搬用ドローンも農業に役立てられることもあります。
例えば収穫した農産物をドローンが運搬することで自ら農地から保管場所への移動を何往復もする必要がなくなるのです。
また免許を持たない高齢の農家でもドローンを使うことで、負担を軽減できる効果があります。
間接的に農業に関わるドローン
ここからは農薬散布や農産物の運搬のような農業に直接的に関わるドローンではなく、生育状況の分析や、周辺環境の監視に使われる間接的に農業に関わるドローンを紹介します。
センシング用ドローン
また、ドローンが作物の上を飛行して、作付の育成状況や土壌、病虫や雑草の発生状況を可視光カメラや赤外線カメラで撮影して観察・分析し、抽出したデータを元に次の作付に活用できるセンシング用ドローンもあります。
動物被害対策用農業ドローン
農薬や肥料を散布するタイプとは異なり、農作物を鳥獣や野生動物から守る用途にもドローンは活用されています。
一般的な可視光カメラや赤外線カメラを積んだドローンが上空から鳥獣や地上に生息している猪や鹿などの生息数や分布を撮影し、画像解析システムを使って分析します。
その分析結果をもとに環境整備などの対策を取ることで、農地を守るという活用方法です。
農業用ドローンの代表的なメーカー
こうした農業用ドローンを生産しているメーカーと代表的な機器を紹介していきます。
DJI JAPAN 株式会社
世界最大のドローンメーカーDJIでは農業用のドローンも生産しています。
農業用ドローンAGRASシリーズの最新版、AGRAS T50は、40 kgの噴霧ペイロードまたは50 kgの散布ペイロード積載可能で、両眼ビジョンセンサーとデュアルレーダーを搭載しているため、安全性と安定性を実現しています。
4つのスプリンクラーによる噴霧が可能で、流量率毎分24 Lで、スムーズかつ広範囲で農薬散布が可能です。
またDJI AGRAS T50は、障害物迂回機能と地形フォローに対応し、最大20°の斜面にある果樹園の測量業務が可能です。
そのため、農薬散布だけでなく、測量も可能なため、より高精度な農薬散布を実現できるのです。
農地が広範囲で何度も農薬散布をする機会が多い方にお勧めの機体と言えます。
株式会社ACSL
千葉大学発のベンチャーとして創業した国内産ドローンSOTEN(蒼天)は、複数のカメラを搭載可能で、鳥獣の出没や捕獲状況の把握にも活用されています。
広範囲・夜間など、さまざまな状況・角度からほ場の確認を行いたい、鳥獣被害から農作物を守りたいという農家の方にはお勧めの機体です。
ACSL製品はセキュリティを重視し、政府調達にも使われる国産ドローン。センシング・監視用途での活用がメインで、農業向け用途でも注目されています。
株式会社FLIGHTS
株式会社FLIGHTSは、2018年に株式会社FLIGHTSにより設立された農業ドローンブランドです。現在は株式会社スリー・エスが運営しています。安価で、安全に活用できるということが大きな特徴です。
最新機材FLIGHTS-AG V2は、一人で持ち上げ可能な軽量設計が特徴で、アームとプロペラを折りたたむと、車への積みおろしや収納も楽々なコンパクトさも兼ね備えています。
1haあたり10分で薬剤散布が可能なだけでなく、粒剤散布装置と付け替え可能なため、液剤だけでなく種まきや追加で粒上の肥料を散布できるのも大きな特徴です。
自動帰還モードや、肥料を散布する一辺を指定することで以降の散布飛行を自動で行ってくれるモードもあり、農業用ドローン初心者の方にお勧めの機体です。
ヤマハ発動機株式会社
ヤマハ発動機がドローン市場に参入したのは2018年、それまで農業の負担軽減策としては無人ヘリコプターでの農薬散布でしたが、購入に1,000万円以上かかり、操縦には高度な技術を要するため、個人農家が所有するには高いハードルがありました。この課題を解決すべくドローン市場に参入したのです。
水稲の肥料や農薬散布だけでなく、野菜や豆類の畑作、松や果樹と言った木に対しても使える機材です。
専用バッテリーはTDK株式会社(ATL)と、産業用モーターは日本電産株式会社と共同開発しました。国産メーカーのモノ造り技術で生産し、信頼性が高く高品質な機体であることも特長の一つです。
株式会社マゼックス
株式会社マゼックスは農薬散布・防除・運搬など産業用ドローンの納入実績は国内メーカーNo.1の実績を誇ります。
最新農業用農薬散布ドローン飛助MG/DXは、大型の農薬散布ドローンでありながら、1つのバッテリーで最大16L=2haを薬剤散布できます。
大型の散布用タンクを搭載しながらも、強風時でも非常に安定したホバリング性能で、飛行中の高度維持や姿勢制御も精密に行い操縦者の負担を減少させます。
稲作など広範囲の農薬や肥料散布におすすめな農業用ドローンです。
農業用ドローンの用途と活用のメリット
多種多様な農業用ドローンがあることは分かりましたが、実際農業の現場に導入してどのようなメリットがあるのか紹介していきます。
農業用ドローンのメリット①コスト削減
農薬の散布や種を捲く際に、これまで無人または有人ヘリコプターを使用すると、ヘリコプターの購入は相場で1,000万円以上かかり、農協へ散布を委託する場合でも約50ha当たり年間150万円ほどの費用負担が発生していました。
農業用ドローンは購入すると100万円~300万円程度の費用に抑えられて、年間の維持費も一般的には10万円~20万円前後となっているので、ヘリコプターに比べてかなりのコスト削減を実現できます。
勿論保有している農地の広さによって農業用ドローンを購入するよりも共同保有や農協に委託した方がより安く済む場合もありますし、小規模の場合はドローンを導入するよりも費用を抑えられる方法もありますので、まずは農地の広さやドローンを導入したことによるメリット・デメリットをまとめることをお勧めします。
農業用ドローンのメリット②労働負担の軽減
農地の管理や収穫は従事する方たちにとって大きな負担です。
農業用ドローンを活用することで、一定の地点から動かずに肥料や農薬散布を行うことが可能です。また、単に農作業を軽減させるだけではなく、ドローンにカメラやセンサーを設置すれば、農作物や圃場全体の状況をデータで管理できるようになります。これだけでも大きな負担軽減となります。
さらに、ドローンから収集したデータを分析して蓄積すれば、次回以降の農作物栽培にもデータを活かして効率的に畑つくりをすることも可能です。
農業用ドローンのメリット③農薬散布だけでなく生産管理や害獣対策に応用可能
農業用ドローンは農薬や肥料散布だけでなく、機材によっては同じ農場を飛行させ続けることで、リアルタイムで農作物の生育状況や、農作物の病気や生育ムラも確認できます。
さらに赤外線サーモグラフィーカメラを搭載しているドローンであれば、夜間の監視も可能なため、害獣対策に役立てることもできるのです。
農業用ドローンの導入事例
実際に農業用ドローンを農場などで活用された事例を紹介します。
事例①中山間地スモールスマート農業実証プロジェクト
ヤマハ発動機のドローンは、浜松市の「中山間地スモールスマート農業実証プロジェクト」に採用されました。
このプロジェクトは、小規模で分散した中山間地の農地でのスマート農業普及をめざすもので、農家とヤマハ発動機などの農機メーカー、地域の農業団体などが協力して実証実験を行っています。
実証実験が実施されているのは、市内の中山間地域にある春野町。春野町では、機械を導入しにくい斜面での重労働や、農家の担い手不足が課題となっており、ドローンによる省力化が期待されています。
春野町内で特産の切り干し大根向けの大根を栽培している「笑顔畑の山ちゃんファーム」(山下光之代表)のほ場で、ドローンによる液体肥料の散布やセンシングによる生育管理などを実際に行っています。
2020年11月の見学会では、実際に約1,000平方mにドローンで肥料散布を行い、高い精度の肥料散布が5分程度で完了することが紹介されました。従来の手作業から大幅な時間の短縮を可能にしました。
事例②ドローンによる梨の溶液授粉の実証
地球温暖化や農薬の影響によってミツバチの活動が低下したことで、特に気温が高い夏場には自然受粉が困難になる場合があります。この受粉を促すために農業用ドローンが活用されました。
梨の人工授粉では、花粉が含まれる溶液をドローンで散布する方法が導入されています。
ドローンによる梨の溶液授粉の実証試験を2019年に和梨、洋ナシ)で試験的に実施しました。
ドローンで樹上約2メートルの高さから溶液を均一に散布し、4⼈の作業員が10アールを約1⽇かかる授粉作業を1機1分程度で終了させることができました。
作業の効率化により、複数回の授粉が可能となり、今後は6〜7割の着果率を⽬指しているということです。農業用ドローンの導入で作業効率化と着果率の向上が期待されています。
農業用ドローンを導入する際の注意点
農業用ドローンの活用事例やメリットは分かりましたが、実際に導入する際どのような点に注意すればよいのでしょうか?農業用ドローンを導入する際の注意点をおさらいします。
①講習や資格、免許などの制度を理解する
よくドローンの操縦には免許が必要では?と疑問を持たれる方も多いですが、農業用ドローンの操縦自体には運転免許のような資格は必要ありません。
ただし、農林水産航空協会が定める性能試験に合格した農水協認定機や、DJI・クボタの農業用ドローンを購入するためにはメーカーや協会の定める技能認定が必要になるケースもあります。
資格取得にも10万円以上の費用が掛かり、教育施設での講習は数日以上になることもありますので、講習や資格については農業用ドローン導入前によく確認しましょう。
②補助金などが活用できるか調べる
農業用ドローンの機体購入費は、100~300万円程度と言われており、かなり高価です。
農家への負担を軽減するため、農業用ドローンを導入する場合、導入費用の一部を補助金で補填できます。
また、農業用ドローン本体だけではなく、自治体によってはライセンス取得費用も補助金・助成金の対象となることもあります。
法人だけではなく個人事業主が利用できる場合があるので、それぞれの応募条件をよく確認し、必要な書類などを把握して補助金が活用できるか調査してみましょう。
③保守費用を確認する
農業用ドローンは導入後にも保守費用が掛かります。
かかる主な保守費用は、ドローンの機体保険料や賠償保険料、点検・メンテナンス費用が該当します。加えて部品が破損・紛失したなど、運用時に発生した部品の購入費用などが挙げられます。
メンテナンス代や保険料を含めると1機あたり10万円~50万円くらいはかかると言われています。
農場が広さや、保有しているドローン機数などによっても異なりますが、導入前にどのくらいの保守費用が年間でかかるのか算出しておくことをおすすめします。
まとめ
農業用ドローンは、農家の負担軽減や少子高齢化に伴う農業人口の減少に対して有効なソリューションと言えます。
様々な事例で実際活用が進んでおり、今後、技術の進化に伴い、農業において欠かせない存在となる可能性が高いでしょう。
農業用ドローンの導入にご興味をお持ちの方で導入方法や保守について詳しく知りたい方はドロサツ‼にお気軽にお問い合わせください。
 ログイン
ログイン