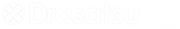ドローンの活用が広がるにつれ、事故やトラブルに備える「ドローン保険」への関心が高まっています。業務利用に限らず、趣味での飛行であっても万一のリスクは避けられません。
本記事では、ドローン保険の基礎から選び方までを網羅的に整理し、操縦者が安心して飛ばせるためのポイントを解説します。

なぜドローンに保険が必要なのか
ドローンは便利で身近になった一方、落下や衝突による事故リスクを常に伴います。
測量中に制御不能になったり、イベント撮影で観客に接触したりする可能性はゼロではありません。事故が発生すれば、壊れたドローンの修理費用だけでなく対人・対物の賠償責任が発生します。
こうしたリスクに備えるのが「ドローン保険」です。
ドローン保険の主な種類
ドローン保険には複数の種類があり、それぞれ対象や補償範囲が異なります。
賠償責任保険
第三者に対する賠償責任を補償する最も基本的な保険です。
建物の損壊や通行人へのケガなど、想定外のトラブルに備えられます。業務利用では必須といえるでしょう。
保険会社によっては、1億円・3億円・5億円などの保険金が設定されている商品もあり、飛行の難易度や飛行させる場所によって選ばれています。
機体保険(動産総合保険)
ドローン本体の破損や水没を補償します。特に高額な機体を業務で頻繁に使用する場合には安心です。
搭載機器・貨物の保険
カメラや測量機器などを搭載している場合、それらを対象とする保険もあります。映像制作や測量など、専門用途では重要な選択肢です。
包括型保険
企業や団体が複数のドローンを運用する場合に適した契約方式です。管理を一本化でき、コストや手続きの効率化につながります。
加入時にチェックすべきポイント
ドローン保険を選ぶ際には、単に「補償があるかどうか」だけではなく、契約条件や利用環境に照らして適切かどうかを見極める必要があります。
ここでは特に注意すべきポイントを整理します。

補償範囲の明確化
「対人・対物のみ」か「機体や搭載機器まで含む」かによって安心感は大きく変わります。
たとえば空撮中にカメラが破損した場合、それが補償対象でなければ全額自己負担になります。自分が守りたい対象を明確にしてから契約を検討しましょう。
飛行エリアや用途の制限
人口集中地区(DID)や夜間飛行、目視外飛行、農薬散布など特殊作業は、補償の対象外となる場合があります。
自身の飛行スタイルや用途が制限に当てはまらないか必ず確認することが重要です。
免責金額と保険料のバランス
保険料が安くても、免責額が高ければ実質的に補償されない可能性があります。例えば免責が5万円なら、それ以下の修理費用は自己負担です。保険料と免責のバランスを見極め、総合的に安心できるプランを選びましょう。
契約単位と利用頻度
保険には「年間契約」と「スポット契約(一日単位など)」があります。
頻繁に飛ばす場合は年間契約が安心ですが、旅行やイベント時のみならスポット契約が無駄なく便利です。利用頻度に合った契約形態を選びましょう。
保険会社・取扱代理店のサポート体制
事故時の対応スピードは極めて重要です。
24時間受付があるか、オンラインで申請できるか、業務利用での緊急対応が可能かなどを確認しましょう。サポート体制が不十分だと、トラブル時に大きな損失を招く可能性があります。
追加オプションや特約
保険によっては以下のような特約を追加できる場合があります。
- 操縦者自身の怪我をカバーする傷害保険
- 複数機体をまとめて管理する包括特約
- 農薬散布や測量など特殊用途向けの補償
自分の運用に合うオプションがあるか確認しておくと安心です。
個人と法人で異なるニーズ

個人利用の場合
旅行や趣味での空撮には、最低限の賠償責任保険でも安心感があります。
一日単位で加入できる「ワンデイ保険」も選択肢の一つです。
法人利用の場合
建設・点検・測量・農業など業務利用では、包括的な補償が求められます。対人・対物だけでなく、機体や搭載機器も網羅したプランが適しています。
近年の制度改正と保険の関係
2022年の航空法改正により、100g以上のドローンが規制対象となりました。
登録制度やリモートIDの義務化に加え、保険加入を推奨する流れが強まっています。事業者の場合、取引先から保険加入証明の提示を求められるケースも増えています。
ドローン保険と教育・講習の関係
保険は万一に備える仕組みですが、事故を防ぐには操縦技術や知識も不可欠です。
DJI正規ディーラーなどが提供する講習では、機体操作だけでなく法規制や安全運用について学ぶことができます。保険と教育を組み合わせることでリスクを最小化できます。
▼DJI JAPAN株式会社による民間資格について
保険を選ぶときの具体的ステップ
- 利用目的(趣味/業務/団体運用)を整理する
- 必要な補償範囲を明確にする
- 複数の保険会社やディーラーのプランを比較する
- 飛行エリアや業務内容に制限がないか確認する
- 操縦講習や安全管理とあわせて検討する
こうした手順を踏むことで、自分に合ったプランを選びやすくなります。
まとめ:安心して飛ばすために
ドローンは映像、測量、農業など幅広い分野で活用されていますが、同時にリスクも抱えています。ドローン保険は事故から操縦者と周囲を守るために欠かせない備えです。
さらに、正しい知識や講習、安全運用体制を整えることが事故防止につながります。ドローンを「安心して」「長く」活用するために、保険は重要な役割を果たします。
私たちもレンタル・販売・講習といった現場に携わる中で、保険と教育がドローン普及の両輪であることを実感しています。
安心して空を楽しむために、まずは自身の飛行スタイルに合った保険を検討してみてください。
▼レンタル・販売のほか、講習やパイロット派遣、データ解析などさまざまなサービスを提供しています
 ログイン
ログイン